こんにちは。あくまきが大好きなスーグル(@vsoogle)です。
鹿児島県民なら馴染みのある「あくまき」。
鹿児島県民以外の方は初めて聞く名前だと思う。もしかしたらケンミンショウ的なテレビで見て名前は知っている方もいるかもしれない。
今回はあくまきの作り方についての記事。
2017年のGWにあくまき作り体験イベントがあったので、それを参考に紹介。
あくまきとは?

あくまき(灰汁巻き)とは、鹿児島県、宮崎県、熊本県人吉・球磨地方など南九州で主に端午の節句に作られる季節の和菓子である。もち米を灰汁(あく)で炊くことで独特の風味と食感を持つ。
出典:Wikipedia
作り方
もち米を測る

作るサイズにもよるが、今回は約100グラム。
笹の皮でくるむ

笹の皮はスーパーで売っている。特にあくまきの時期は沢山売られている。

笹の皮にもち米を載せ、綺麗に包む。
笹の紐で縛る

笹の皮の紐でしばる。

これで下準備は完了。
灰汁で煮込む
イベントであくまきを作った時はドラム缶を使用。家で行う時は圧力鍋が良いらしい。


大量にあくまきを入れていく。


あくまきを火にかけ、約2時間待つ。
完成

2時間経過し、ザルに取り出す。

紐を解き、中身をチェック。

笹の皮を開いてみると、良い感じのあくまきが!
まとめ
あくまきは鹿児島県民のソウルフード。

しかし、今回驚いたのは、鹿児島県民はあくまきは食べたことはあっても、作ったことある方は少ないということ。今はスーパーでも売ってるし、自分達で作るという家庭は少ないのかもしれない。





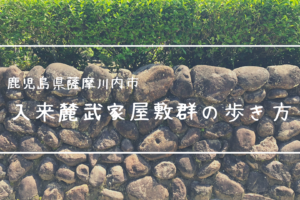




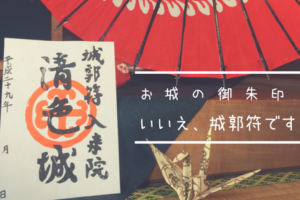
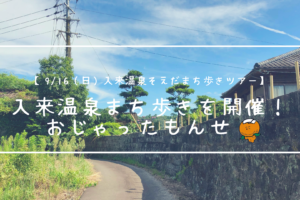










コメントを残す